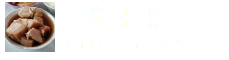DRINK ON EMPTY STMACH 003 - 4
2010年1月4日
究極の読書考
世界で唯一の幸福な読者
幸福な読書なのか? 神級の超絶職能なのか?
松本清張・専属速記者のものすごい話で、3杯目。


〔究極の読書〕の前提条件は、超人・松本清張
文藝春秋の「日本の黒い霧」連載の仕事をきっかけに、福岡隆さんは松本清張氏の小説の口述速記も担当するようになりました。当時、清張さんはある女性の速記者を雇って小説の口述をしていたのですが、その人が事情でやめることになったため、同時期に「日本の黒い霧」を速記していた福岡さんが引き継ぐことになったのです。
その後、福岡さんは、他の仕事を完全に整理して松本清張・専属の速記者となり、9年もの長きにわたって、清張さん本人に新しい小説を毎日のように語り聞かせてもらう(&速記)という、至福の悦楽ライフに突入したのでした。(昭和34年から43年までの9年間に、400字詰め原稿用紙で7万枚!単行本にして80冊!)
福岡さんにお会いして話を伺うにあたり、筆者は、『松本清張の新作に世界でいちばん最初に接する唯一の人』『まだ発売されていないどころか、まだ紙に書かれてもいない、新作中の新作を、世界でただ一人独占する至福』といったことを想像し、『それは仕事というよりも、あまりにも幸福な究極の読書だったのではなかろうか』と考えたわけですが、そうであるためにはひとつ条件があります。
松本清張氏の口から放たれる内容が、その時点ですでにほぼ完成された小説の文章になっていなければならないのです。
例えば清張さんの口述が……
『りんごを拭いて艶を出していた四十ばかりの店主が……いや、りんごじゃなくて紅玉にするか……年も五十がらみのほうがいいかな……紅玉を拭いて艶を出していた五十がらみの店主が……うーん、雑貨屋のほうがいいかな……』
……というような具合に、迷ったり直したりしながらわずかずつ進んで行くものだったりすると、それを聴くのはもはや〔読書〕とはかけ離れた行為になってしまう。
その点を、福岡さんにお会いした際まっ先に尋ねたのですが、答は「喋りがもうそのまんま小説の文章になっていた」でした。
福岡さんによれば、
「あの分厚い唇から、次々と文章体で小説が語られる」
「ほとんど完成された小説を朗読している……という感じ」
「普通は誰でもある程度は口語体になってしまうもので、とうていそのまま文章にはならないのだけれど、松本清張さんは違った」
「長い速記生活の中で、こんな人はほとんど見たことがない」
超人・松本清張。
ただ、それが何時間でも続くのかというと、超人といえどもやはり人間、長丁場になると、口述だけに「文章が流れる」感じになってしまうので、時々休憩をはさみながらだったそうですが……。
ちなみに、これからいよいよ小説を口で喋る時はどういう感じであったのかというと、
書斎の洋机に座り、原稿用紙に1行だけ「〇〇について」といった見出しを書き、机の前の壁に向かって喋り出す。
速記をする福岡さんに面と向かって口述するのではなく、《机に座り》《壁に向かって》というところが興味深い。ここらへんが作家の生理というか、口述であっても『執筆』であるということなのでしょうか。
小説には会話もあります。会話の部分では、清張さんはその人物になりきって喋っていたそうです。例えば女性のセリフは女言葉でちゃんと言う。
「清張さんが、あのいかつい容貌に似合わない裏声を出して、女になりきって喋る」
「最初はおかしくて何度も吹き出してしまった」
また、清張作品の舞台は全国各地にわたりますが、地方の舞台設定の時は、方言の会話もそのまま演じるように喋っていたそうです。出身の福岡弁はもちろん、関西弁、広島弁もとても上手。ただし、東北弁だけは苦手なようで、福岡さんの奥様(弘前出身)に津軽弁への翻訳を頼んだこともあったという話でした。